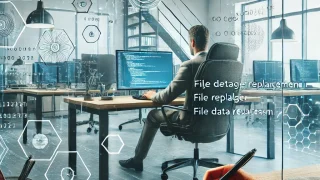 C#
C# C言語ツールで簡単にファイルデータを置換する方法
文字列置換はサクラエディタを使用すると楽ですが、サクラエディタを使用した場合は大量データの処理ができないという問題があります。そこで、C#をプログラムにより置換を行うというのが有効になります。プログラムでのファイルのストリーム読み込みであれ...
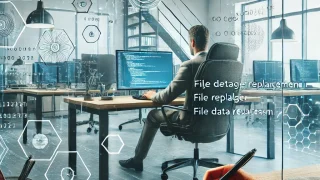 C#
C#  C#
C# 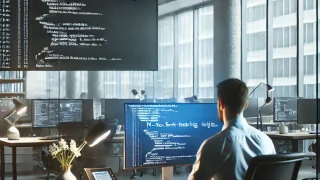 C#
C#  java
java 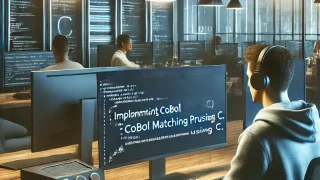 C#
C#